「トイレが近くなるから、あまりお水は飲みたくないんだよね…」
高齢の親御さんから、こんな言葉を聞いたことはありませんか?年齢を重ねると、若い頃のように喉の渇きを感じにくくなる一方で、水分摂取をためらう様々な理由が隠されています。しかし、これからの季節、特に注意したいのが脱水症状や熱中症のリスクです。高齢者にとって、水分補給は健康維持に不可欠。この記事では、高齢者が水分を控えがちになる具体的な理由と、ご家族が無理なくサポートできる水分補給の工夫、そして何よりも大切な「寄り添う気持ち」について詳しく解説します。
なぜ?高齢者が水分を控えがちになる5つの理由
ご高齢の親御さんが水分を避けるのには、ご本人なりの切実な理由があります。まずは、その背景を理解することから始めましょう。
- トイレが近くなることへの抵抗感:恥ずかしさや面倒くささ
頻繁にトイレに行くことに対して、「周りに迷惑をかけるのでは」「何度も席を立つのが億劫」といった気持ちを抱く方は少なくありません。特に外出時や誰かと一緒にいる場面では、その傾向が強まることがあります。また、足腰が弱ってくると、トイレへの移動自体が負担になることも考えられます。 - 夜中にトイレで目が覚めることへの懸念
「夜、何度もトイレに起きると熟睡できない」「睡眠不足は体調を崩す原因になる」といった思いから、就寝前の水分摂取を控える方は非常に多いです。質の高い睡眠を求める気持ちが、かえって水分不足を招いてしまうことがあります。 - 喉の渇きに気づきにくい:加齢による身体の変化
私たちの身体は、体内の水分量が減ると喉の渇きを感じるセンサーが働きます。しかし、加齢とともにこのセンサーの感度が鈍くなる傾向があります。そのため、身体が水分を必要としている状態でも、ご本人は「喉が渇いていないから大丈夫」と判断してしまうことがあります。 - 冷たい飲み物への苦手意識
「冷たいものを飲むとお腹を壊しやすい」「身体が冷えるのが嫌」といった理由で、特に冷水や冷たいお茶を避ける方もいらっしゃいます。若い頃は平気だったとしても、年齢とともに体質が変化し、冷たいものが身体に合わなくなってくることがあります。 - 「水分摂取=病気」という誤った認識
「水やお茶を積極的に飲むのは、お医者さんに指導された病気の人がすること」というイメージを持っている方もいます。健康なうちは特に意識して水分を摂る必要はない、と考えてしまうのかもしれません。このような誤解が、日常的な水分補給の妨げになっている可能性があります。
これらの理由から、知らず知らずのうちに「水分を摂らない」ことが習慣化してしまっている高齢者は少なくありません。
水分不足が招く、見過ごせない健康リスク

高齢者の場合、若い世代よりも体内の水分量が少ないため、少しの水分不足でも様々な健康リスクを引き起こしやすくなります。
- 脱水症状
初期には口の渇き、皮膚の乾燥、尿量の減少などが見られます。進行すると、頭痛、めまい、吐き気、意識障害などを引き起こし、命に関わることもあります。 - 熱中症
高齢者は体温調節機能も低下しているため、暑さを感じにくく、熱中症になりやすい傾向があります。室内でも発症するケースが多く、特に夏場は注意が必要です。 - 脳梗塞・心筋梗塞
体内の水分が不足すると血液の濃度が上がり、ドロドロの状態になります。これにより血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まります。 - 便秘
水分不足は便を硬くし、排便を困難にします。慢性的な便秘は食欲不振や腹部膨満感など、QOL(生活の質)の低下にも繋がります。 - 認知機能の低下
脱水状態が続くと、脳の働きが悪くなり、集中力や記憶力の低下、混乱などを招くことがあります。
これらのリスクを理解し、日頃から適切な水分補給を心がけることが、高齢者の健康を守る上で非常に重要です。
無理なくできる!今日から始める水分補給5つの対策
では、どのようにすれば高齢の親御さんに無理なく水分を摂ってもらえるのでしょうか。ここでは、今日から実践できる具体的な対策を5つご紹介します。
- 時間帯を工夫する:「夜間ではなく日中にこまめに」を合言葉に
夜間の頻尿を気にされる場合は、就寝前の水分摂取は控えめにし、その分、日中にこまめに水分を摂るように促しましょう。例えば、「朝起きた時」「朝食後」「午前10時頃」「昼食後」「午後3時頃」「夕食後」など、生活の節目に水分補給のタイミングを設けるのがおすすめです。特に活動量の多い日中や、入浴前後、運動後などは意識して水分を摂るように声をかけましょう。「夕方17時以降は、温かい飲み物を少量だけにする」など、ご本人の不安に寄り添った調整も大切です。 - 温かい飲み物でホッと一息:白湯や温かいお茶のすすめ
冷たい飲み物が苦手な方には、白湯や温かいお茶、ハーブティーなどがおすすめです。常温よりも少し温かい程度の飲み物は、身体への刺激が少なく、喉越しも滑らかで飲みやすいと感じる方が多いようです。生姜湯や葛湯なども身体を温める効果があり、美味しく水分補給ができます。親御さんの好みに合わせて、いくつかの選択肢を用意しておくと良いでしょう。 - 生活習慣に自然に組み込む:「お薬と一緒に」「食後に一杯」
水分補給を特別なことと捉えず、日々の生活習慣の中に自然と組み込むことが継続のコツです。「朝のお薬を飲む時には、コップ一杯のお水も一緒に」「食事が終わったら、温かいお茶を一杯飲む」といったように、他の行動とセットにすることで、抵抗感を減らし、習慣化しやすくなります。ご家族が一緒に同じタイミングで水分を摂るのも良い方法です。 - 優しい声かけで「一口から」:プレッシャーを与えない工夫
「たくさん飲んで!」と強く促すのではなく、「喉が渇いていませんか?」「少しだけでもお茶をどうぞ」といった優しい声かけが大切です。「一口だけでもいいから飲んでみない?」と少量から始めることで、ご本人の負担感を軽減し、「それなら…」と受け入れてもらいやすくなります。「美味しいお菓子があるから、お茶と一緒にどう?」といった、楽しみと結びつける誘い方も効果的です。 - 「食べる水分」も上手に活用:スープ、ゼリー、果物も立派な水分源
どうしても飲み物で水分を摂るのが難しい場合は、食事から水分を補給することも意識しましょう。具沢山の味噌汁やスープ、お粥、煮物などは水分を多く含みます。また、ゼリーやプリン、ヨーグルト、果物(スイカ、梨、みかんなど)、野菜(きゅうり、トマトなど)も手軽な水分源となります。デザートやおやつとして、これらの食品を上手に取り入れてみましょう。
「飲ませる」のではなく「一緒に整える」:寄り添う気持ちが最大のサポート
高齢者への水分補給において最も大切なのは、「無理強いしないこと」そして「本人の気持ちに寄り添うこと」です。頭ごなしに「飲みなさい」と指示するのではなく、「どうしたら心地よく水分を摂れるか」を一緒に考え、環境を整えていく姿勢が求められます。
- コミュニケーションを大切に
なぜ水分を摂りたくないのか、どんなことに困っているのか、まずはじっくりと話を聞きましょう。その上で、水分補給の必要性を丁寧に伝え、一緒に解決策を探していくことが大切です。 - 環境づくりでサポート
手の届きやすい場所に飲み物を常備しておく、お気に入りのカップや湯飲みを用意する、飲み物の温度をこまめに気遣うなど、さりげない配慮が水分摂取のきっかけになることがあります。 - 家族が見本を示す
ご家族自身が美味しそうに水分を摂る姿を見せることも、良い影響を与えることがあります。「一緒に温かいお茶を飲もうか」と誘ってみるのも良いでしょう。
時には、言葉での声かけよりも、そっとテーブルに置かれた一杯の白湯の方が、親御さんの心に響くこともあります。焦らず、根気強く、そして何よりも愛情を持って接することが、高齢の親御さんの健康を守るための最も効果的な「お薬」なのかもしれません。
まとめ
高齢の親御さんが水分を控える背景には、様々な理由があります。それらを理解した上で、ご本人の気持ちに寄り添いながら、無理なく続けられる水分補給の工夫を見つけていくことが大切です。脱水症状や熱中症のリスクを避け、健やかな毎日を送るために、今日からできることから少しずつ始めてみませんか。ご家族の温かいサポートが、何よりも大きな力となるはずです。
関連リンク:
- 環境省 熱中症予防情報サイト 高齢者のための熱中症対策: https://www.wbgt.env.go.jp/heatstroke_project_senior.php (環境省の熱中症予防に関する啓発資料などが掲載されています)

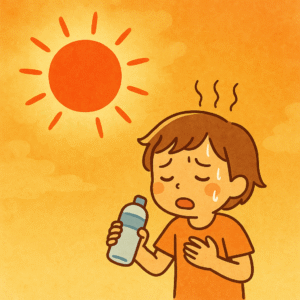




コメント